会員お楽しみの一つ、ボランティア研修旅行。一時コロナ禍のため途絶えていましたが、昨年から再開。去年は塩狩峠へ行きました。
さて今年は?滝上町へ行ってまいりました。綾子さんの夫君三浦光世さん(当館第二代館長)が幼年時を過ごした町です。旭川から東へ車で2時間半ほどの距離。オホーツク海内陸の町。
5月12日月曜日 天気予報も晴れ。暑くもなく申し分ない旅行日和です。
8:30 参加者総勢24名。いざ文学館出発。
50名は乗れるかという大型バスに乗り込みます。席は一人ずつ余裕で座れるようでした。が、後方席から「山口さん、こっち、こっち」と手招きする人が……。見るとそこにはすでに、おなじみ案内人仲間と喫茶のスタッフさんたちがぎゅぎゅっと席を占めていました。みな小学生の遠足のようにピカピカな笑顔をして、これは楽しそうと、早くも期待に胸がふくらみます。
こういう研修って、見学もためになりますが、仲閒と交わす情報交換もまた得がたいものがありますよね。車中では自然と、各自の知る光世さんの思い出話になりました。私の隣の席のAさんがまた良い質問をしてくれて、座を盛り上げてくれたんですよ。
目的地に着く前に、ここで光世さんの出自を軽く紹介します。
1924年東京目黒の生まれ。4人兄弟の第3子。父は大正の初期福島県から滝上に入植した。(滝上では明治38年に開拓が始まっていた。)
「当時は鬱蒼とした原始林で、木を一本伐り倒すごとに空がひらけ、その空に向って、父や母たちは歓声を上げたという。」(『この土の器をも』より)
苦労して3戸分の土地を拓き、自分と妻の両親一家を呼び寄せた後、父は土地を彼らに預け上京して職に就いた。光世はその時期に生まれた。光世3歳の頃父の肺結核が悪化し一家は滝上に戻った。ほどなく父は亡くなり、母は髪結いになるため札幌へ行ったため、兄と妹は父方の祖父母宅に、光世は一人母方の祖父母宅に預けられて、14歳まで滝上で過ごした。
三浦綾子作品『泥流地帯』の、開拓農村に生きる一家の暮らしぶりが光世幼年時の生活をモデルにしていることは、三浦文学ファンもよく知るところです。貧しさのために中学進学を諦めた耕作。また、母の帰りを待ちわびる兄弟たち。クリスチャンで聡明なお祖父さん。幼い頃の光世の身の上に重なります。
さて、バスの車中では事務局長難波氏より、光世の自伝『青春の傷痕』など作品の一節が紹介され、開拓時代の父親や幼年時の光世のエピソードが語られました。私たちは、幼くして親兄妹と別れ祖父に預けられた光世の孤独・悲哀に思いを馳せつつ車窓に目をやりました。
バスは折良く、木々に囲まれ鬱蒼とした狭い道を行きます。そのとき、「こっちの方だったかな」案内人仲閒のBさんの声。
光世の兄と妹が預けられた祖父の家三浦家は、このあたりの道路沿い左手にあったのではないか。そして、光世さんが預けられた母方の祖父の家宍戸は右側ずっと奥の方にあったように思う、とのこと。
なんと彼女は十数年前に、当の光世さんと三浦文学研究家の森下先生や読書会仲間とともに滝上町まで行ったことがあるというのです。しかし、いやどっちがどっちだったか記憶が……と自信なげです。そこでもう一人、別の機会に(今から数年前、森下先生同行)滝上へ行ったCさんに対して、「どうだったかね」と聞くと、「どうだろう、右側が三浦家跡じゃなかったかな。以前は兄の健悦さんの墓標が目印になったけど、今はそれも見えない…」と言います。結局不明。にしても、この辺りなんですねぇ。一同どっぷりと感傷に浸る。
そこから数十分走ってバスはようやく滝上町内へ。降りると、すぐさま良い香りが漂ってきます。それは芝桜の香り。花の香りがする町ってなんて素敵!丘全部が芝桜におおわれているという芝ざくら滝上公園、さすがです。私は何十年ぶりかでここを訪れましたが、さらにダイナミックになった気がします。ここでは桜もまだ満開です。なにもかもピンク。1時間ほどの滞在でしたが、お花畑の丘を上まで登り、町の西欧風でロマンチックな景観を眺め下ろして大満足でした。
次はいよいよ町文化センター内の小檜山博文学館着。小檜山先生は三浦夫妻と交流があり、三浦関係も展示されていると聞きました。正直なところ私は小檜山作品には疎いので、今回しっかり学んで帰ろうと意気込んで入りました。が、最初のウィンドウ内の展示品を見て、びっくり。トルソーが着ている光世さんの背広!前見頃裏のネーム刺繍が三浦光世、綾子と連名で記されていたのです。さらにゴム印。これまた夫婦連名。日頃から一心同体の二人とはいえここまで……。案内人ら感嘆。これでもうこのコーナーから離れられません。私ごときはなめるように見続け……ハイ時間終了です。待って、まだ小檜山先生の見てない!大急ぎで他の展示を見、おおこれはすごいとか言いつつ走り去りました。最後に先生のすてきな笑顔に「また来ます」。礼!
本当は生原稿とか貴重な物がたくさんあったんですよ(汗)。他の人はちゃんと見学していますから。
待ちに待った昼食は丘の上にある「ハーブティーと軽食のお店 フレグランスハウス」で。ハンバーグセットは良質のお肉にたっぷりとかかったソースまで美味。デザートのミニソフトは滝上産ハッカ味です。出発までハーブガーデンを散歩したり、ベンチで互いの好きな作品の魅力を語り合ったり……絵に描いたような優雅さ。
さて、真相不明のまま終わるかと見えた光世さんのご実家宍戸家と三浦家の位置の一件。旅の最後に郷土館を訪れたとき決着をみました。そこに入館するやいなや「昭和30年代の滝上町農業最盛時住居分布図」という地図が出迎えてくれたのです。
掲示された特大の図に、「これこれ。これでわかった!」
先に入館していたBさん、Cさんが歓喜の声をあげていました。図は光世さんの幼年時代よりはやや下りますが、しっかりと三浦・宍戸の姓が記載されてあります。滝上町に向かって道路左手に三浦与三郎(父方祖父は小三郎)。右手奥に宍戸吉太郎。(光世さんのお祖父さんの名。この頃は既に逝去)光世の話では両家は7、800メートルの距離。滝上駅まで15、6キロ。
帰途の車中、だれともなく「奥まった所に住んでいた光世さんは小学校まで6km、兄さんたちより遠い道を通ったんだね」とつぶやきました。
三浦の父がくじで当てた土地はひどい石地だったり、斜面が多かったり、奥地だったり苦労が多かったようです※1。それゆえに父は切り拓いた土地を親たちに任せて上京して稼がねばなりませんでした。 綾子が初めて三浦の郷里を訪れたとき、伯父達が四十年耕してきたという畠を見て、かわいそうに三浦の父や家族達はこんな石地に一生の夢を託して、遙々福島から渡って来たのかと述べています※2。 宍戸の家は井戸を掘っても水が出なく、天秤棒をかついで水を汲んでくるのが少年光世の日課でした※3。
(参考: ※1「三浦綾子創作秘話」 ※2『この土の器をも』 ※3『青春の傷痕』)
ところで、滝上町郷土館は郷土資料館、生活資料館、SL館から成ります。明治の開拓時代から現在までの農機具など貴重な郷土資料が展示されています。まあその数の多いことったら!
最後の訪問先はおまちかね道の駅「香りの里・たきのうえ」。皆さんコーヒーをオーダーしたり、アイスを食べたり、特産品のハーブ製品や木工芸品を選んだりと大忙し。満足満足。
再び車中。こうして光世さんの郷里を訪れると、光世さんが身近に感じられるね。今はこんなに町が拓けているけど、かつては樹木の生い茂った道や石ころだらけの道を小さな光世さんが一人とぼとぼ通ったのだろうね。極寒の冬はさぞや…などと語り合いました。
しかし、父の開墾の苦労を知ればこそ光世の郷土愛は強かったに違いありません。また、育ててくれた祖父母は情愛深い人でしたから、幸運でした。特に、お祖父さんがたびたび光世にヨブ記など聖書の話を聞かせてくれたからこそ、後の光世があるわけですし。その彼が綾子さんの創作にも数々の示唆を与えてくれたのです。
そんな光世さんの子ども時代を反映した『泥流地帯』。また読みたくなってきたなあ。再び『泥流地帯』マイブーム来そうです。


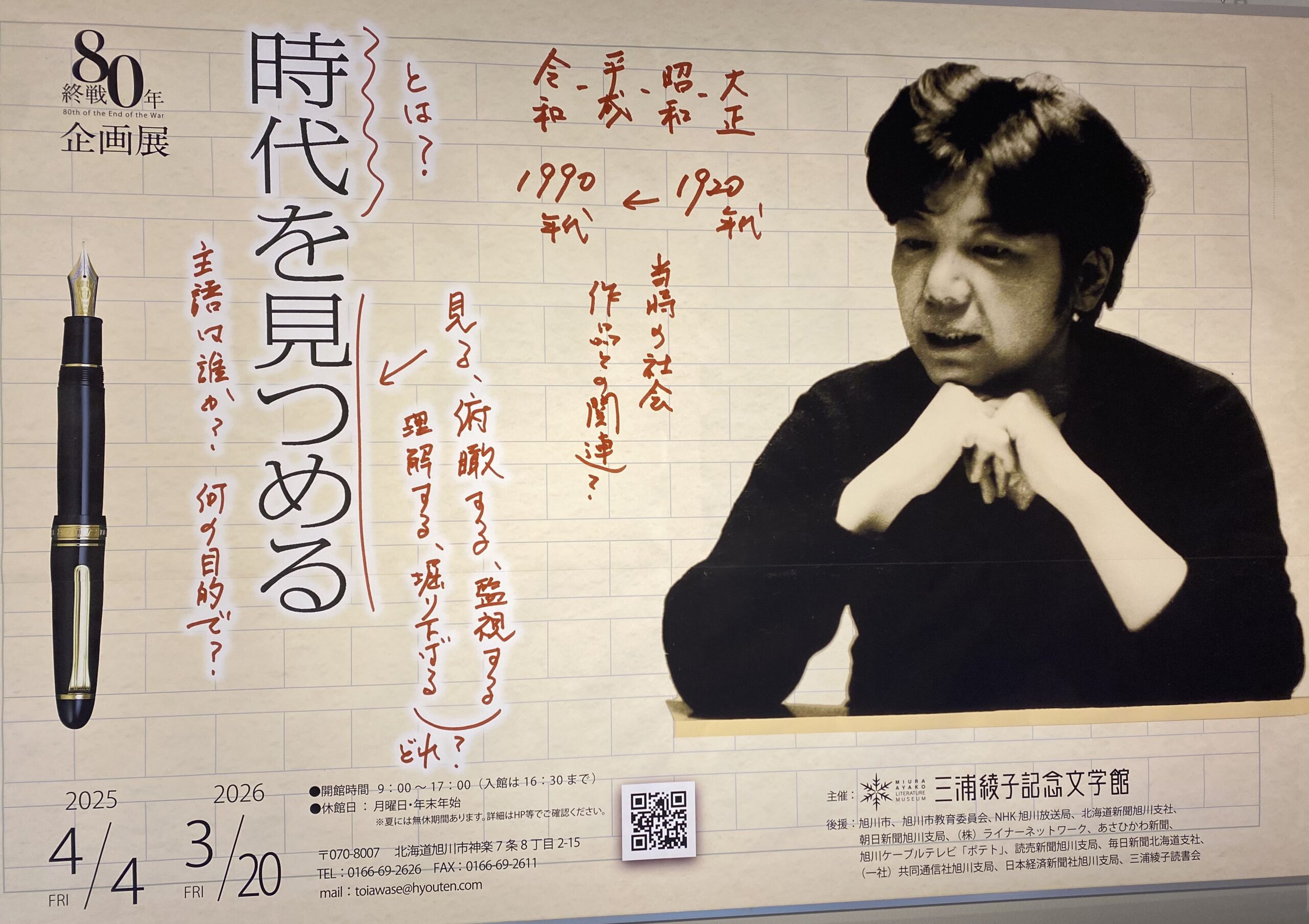

コメント